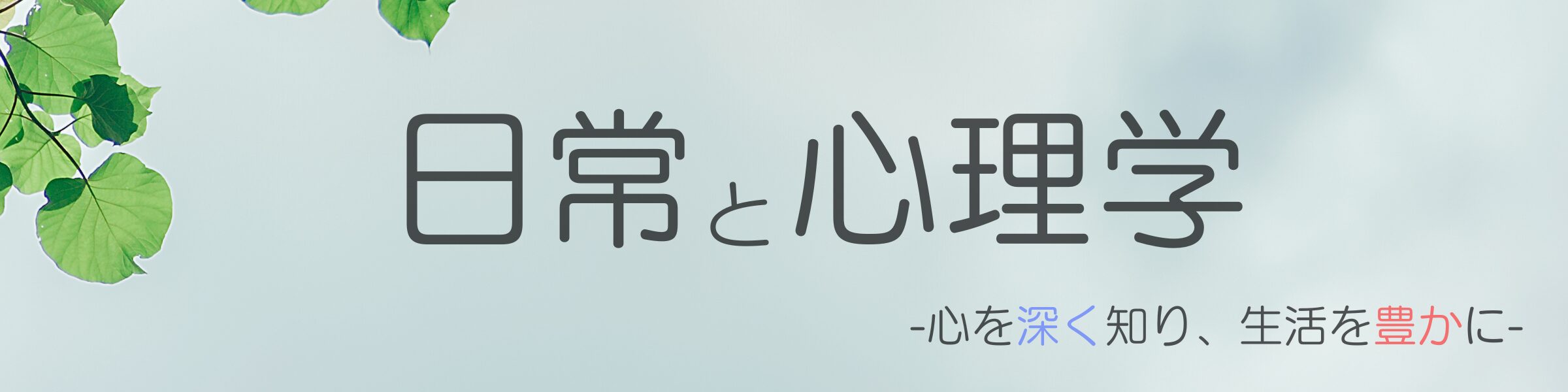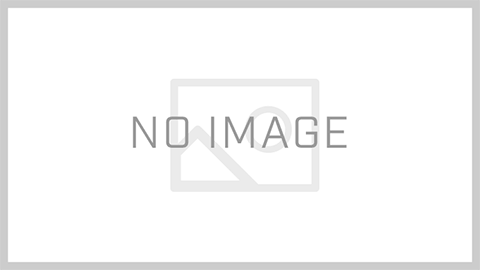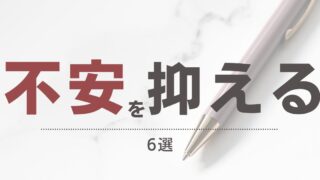「人といると疲れる」
「ひとりの時間は好きなのに、頭の中が休まらない」
「不安をなくしたいのに、考えすぎて眠れなくなる」
そんなふうに感じることはありませんか。
この不安さえなければ人生が明るくなるのに…!!!!
でも、安心してください。
不安は科学的に抑えられることが
心理学や脳科学の研究で明らかになっています。
このページでは、
心理学・脳科学・実証研究をもとに、
内向的な人の「神経症的傾向(不安感度)」をやわらげる方法を解説します。
不安を下げると、人生がどんなふうに変わるのか
まずは、不安を落ち着かせるメリットの一部をご紹介します。
心理学の研究では、
-
集中力が高まり、仕事のパフォーマンスが上がる(Eysenck et al., 2007)
-
人間関係で相手の表情や反応に過剰反応しにくくなる(Gross, 2015)
-
睡眠の質が改善し、自己肯定感が上がる(Harvard Medical School, 2018)
-
感情の波が穏やかになり、日常の幸福度が上がる(Fredrickson, 2001)
つまり「不安を下げる」とは、
単に“気分がラクになる”ということではなく、
あなたの脳のパフォーマンスを最適化し、より自分らしく生きる力を取り戻すことなんです。
「不安を下げる」とは?──心理学で見る不安の正体
「不安」は、脳があなたを守るために作り出す“警報システム”です。
特に内向型の人はこの警報が繊細で、
他人の感情の変化や未来のリスクを瞬時に察知する力があります。
しかし、現代社会ではその“センサーの感度”が高すぎることで、
常に警報が鳴りっぱなしになり、慢性的なストレスを感じやすくなるのです。
神経科学では、この「不安感度」を司るのが扁桃体(へんとうたい)という脳の部位だと分かっています。
そして近年の研究では、呼吸法・日記・認知の習慣などを通じて、
この扁桃体の過剰な反応を前頭前野が抑えられるようになることもわかってきました。
不安を下げるための、科学的に効果のある6つの方法
「不安をなくそう」と頑張るほど、
逆に不安が強くなる──そんな経験はありませんか?
心理学ではこれを「白クマ効果(ironic rebound effect)」と呼びます。
「白クマのことを考えないで」と言われると、
かえって白クマが頭から離れなくなる現象(Wegner, 1994)です。
不安も同じで、“消そうとする”より、“整える”ほうが効果的。
ここでは、神経科学・心理学の研究に基づいて、
内向型でも取り入れやすい6つの方法を紹介します。
① 感情ラベリング
「いま私は〇〇で不安を感じている」と感情を客観視します。
紙に書く・声に出す・チャットで書き残す、どれでもOKです。
「今、不安を感じている」と言葉にするだけで、
脳の中で感情を司る扁桃体の活動が下がることがわかっています。
不安を感じた際は落ち着いて外に吐き出しましょう。
②「今日の3つよかったこと」を寝る前に書く
ポジティブ心理学の創始者セリグマン博士が行った実験では、
「寝る前に、その日によかったことを3つ書く」だけで、
1週間後の幸福度が上がり、うつ症状が有意に下がったと報告されています。
さらに、1週間継続することで6か月間もその効果が継続すると言われています。
これは「脳の反すう傾向」をリセットする効果。
特に内向型の人はネガティブなことを繰り返し考えがち。
何度も考えてしまう癖を、ポジティブなことに向けてあげるだけで、
普段の感じ方が大きくプラスに変わります。
寝る前に3分でできるこの習慣は、内向型の思考の深さを“良い方向”に使うトレーニングにもなります。
③リズム運動
ウォーキング、ヨガ、ストレッチ、ゆっくりした掃除でもOK。
一定のリズムで体を動かすと、
脳内でセロトニンという“安心ホルモン”が安定して分泌されます。
④呼吸瞑想
マインドフルネスや瞑想といわれますが、簡単なのはこの呼吸瞑想。
もちろん効果は絶大です。
目を閉じ、4秒吸って8秒吐く、など吸う時間の倍吐くのがおすすめ。
感情をコントロールする前頭前野の活動が活性化し、
ストレスを感じやすい扁桃体の活動を抑えることが数多く実証されています。
瞑想中、あれこれ考えてしまうのですが、
「今あれについて考えたな。よし、呼吸にもどろう」
というように、考え事をするのがあたりまえで、その都度呼吸(つまり今)
に戻ること自体がトレーニングになっています。
うまくやろうとせず、気軽な気持ちで取り組みましょう。
⑤セルフ・コンパッション(自己への思いやり)
不安を感じたとき、それを責めてはいませんか?
セルフ・コンパッションでは、逆に
「不安を感じる私はなんて人間らしくて愛おしいんだ。」(※脚色あり)
と、自分を認めてあげてください。
不安や自己批判をやわらげる力があると数多くの研究で示されています。
Neff博士の研究では、自己思いやりが高い人ほどストレスホルモン(コルチゾール)の
分泌が低いことが分かっています。
⑥ 睡眠リズムを整える
睡眠不足は、不安脳を最も暴走させる要因です。
睡眠が足りないと、扁桃体の反応が60%以上過剰になるというデータもあります。
内向型の人ほど夜に考えすぎる傾向がありますが、
「寝る時間を固定する」だけで、不安が起こりにくい脳のリズムを作れます。
睡眠は、“最も手軽で効果の高いメンタルケア”です。
個人的特におすすめ3選
すべて一度に行おうとすると難しく、継続も難しくなるため、おすすめを3つ選びました。
①睡眠
②瞑想
③3つのいいこと日記
まず、睡眠ですが、不安を感じやすい人は、そもそも夜ぐっすり眠れることがなかなかないのではないでしょうか。
また、夜中はだらだらしがち。時間を無駄にし、日もまたいでまた睡眠不足。
まずは簡単そうで意外と難しいぐっすり眠ること。
寝る前にいいこと3つ思い出して、ネガティブな気持ちから離れ、
ポジティブな気持ちで眠りにつく。
そして、朝起きてすぐ瞑想。
気軽にルーティン化しやすいのではないでしょうか。
というのも、私自身も、特に睡眠と瞑想には効果を感じており、逆にしないと、調子が明らかに出ないことを実感しております。
また、現在3ついいことを記入するアプリを開発しております。
是非ご活用いただけると幸いです。
効果があって、実生活がよくなった!
このようなお言葉がいつか聞けたら嬉しく思います。
まとめ
- 不安は下げることができる
- 不安をなくすことで人生は大きく変わる
- 不安の過剰反応を抑えるためには扁桃体の活動を抑える
- 不安を下げる方法6つ
- 睡眠 瞑想 日記がおすすめ
いかがでしたか?
不安を感じやすい人は人生が大きく変わるポテンシャルの裏返し。
伸びしろですねぇ!っていうやつですね(笑)
以上!またお会いできれば幸いです!
これはCTAサンプルです。
内容を編集するか削除してください。